~もう米騒動はいやだ!~
「お米の学びなおし講習会」と題した
講習会を受講してきました。
米づくり基礎と収穫までの必要な
ノウハウを学べる、座学3回、
現地講習6回の講習会です。
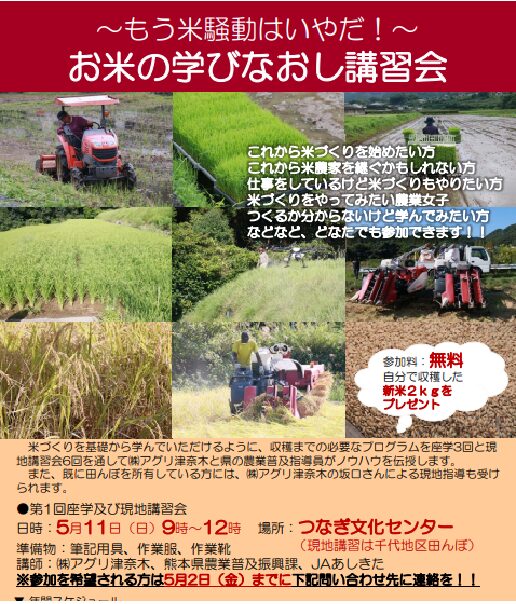
第1回目の今回は、お米のカレンダー
(栽培暦)を基に、「主な作業」「水管理」
「水稲に被害を与える病害虫」を水稲の
生育ステージ(種籾準備から収穫まで)に
沿って説明を受けました。
米づくりに必要な用語解説もあり、
面白かったですよ。
Q1:これ、なんと読む「稚苗」
Q2:1反はなんa(アール)?
Q3:1俵の体積はなんkg?
Q4:1町はなん㎡?
Q5:下の写真、この生き物は何?

答えは後ほど。
座学の後は圃場での実地講習。
今回は「種子消毒」「浸漬・催芽」
「苗床への播種」について、
自家消費(小規模栽培)での昔ながらの
やり方、機械を利用した方法について、
圃場で実演・解説をして頂きました。

↑「お米の学びなおし講習」の発起人で講師の、
㈱アグリ津奈木 坂口 信行 社長。
園主に講習会の参加を誘ってくれた方です。

ブルーシートの上で手作業で行う、昔ながらの
播種の方法。1反(10a)で育苗箱20枚が
目安なので、手作業はなかなか大変です。

機械作業で「播種」「覆土」「施肥」を一度に。
機械作業は早い、正確、省力ですね。
【今日のポイント】
上記、「施肥」ですが、一般的には
圃場(田んぼ)で手散布もしくは機械散布
されるます。今回は肥料メーカーさんも
参加されていて、育苗箱(播種の段階)に
肥料を施し、そのまま収穫まで一切の
肥料を必要としない方法(商品)を紹介
頂きました。これはかなりの省力化ですね。
芦北地域では全体の30%がこの方法に
切替わっているそうです。
最後に問題の答え。
Q1:ちびょう
Q2:10a(アール)
Q3:60kg
Q4:約10,000㎡
Q5:ジャンボタニシ(スクミリンゴガイ)
